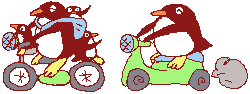冬の薫製

厳寒期に手作り楽しむ
前に薫製のことを書いたときは、「家庭でできる簡単薫製」という話だった。しかし、本当の薫製シーズンは激寒期。手作りの生ハムなどを楽しむちょっと本格的なウインターライフに触れる意味でも、今の時期にもう一度薫製をとり上げておきたい。
強い火を入れ、物理的に熱で殺菌してしまうような熱薫とは違い、じっくり時間をかけて中低温で煙の成分を中まで染み込ませる温薫などの場合、寒いころがいいのである。簡単にいえば、肉や魚をずっと干しておいても腐らない時期ということだ。
薫製は、その昔、洞窟生活の狩猟民が獲物の肉を焚火の近くでつるしていたことから生まれたという説もあるほど歴史ある保存食。
気候の寒暖にかかわらず、世界中に煙の風味と塩の殺菌作用を利用する食文化というのは存在する。
しかし、一般に薫製が現在まで成長してきたのは、涼しい地域ということになる。アメリカやヨーロッパの北部が中心だろう。温暖な地域と違い、冬は獲物が少なくなるので、手に入った肉や魚は少しの期間保存する必要もあったわけだ。
そういうところでは、イラストのように庭の一隅にレンガのスモークハウスが造りつけられ、長時間煙をかけることが可能になっている。日本でも、脱サラして山に入り生活するのが流行したとき、そうしたスモークハウスを造りつけた人もあったようだ。
1週間以上、塩とスパイスで調味した液につけこみ、冷やす。これを流水で塩抜きしたあと、スモークハウスでじっくりつるし、待つこと数時間、素晴らしい夕食ができあがるわけだ。
内臓をとって割箸などをつっかえ棒にして腹を開き、日陰に干す。ここでよく乾燥させることが薫製を成功させるコツ。だからこそ寒い時期がいいわけだ。
イワナの肌に煙が独特の光沢を与え、えもいえない美味に仕上がる。保存食ということなど忘れ、一気に食べてしまうに違いない。アウトドア雑誌が冬になるとナイフの特集をするのは、スタッフがこの美味を楽しむためではないかと私は思っている。
1996,2,15
文:石井研二 絵:石井光