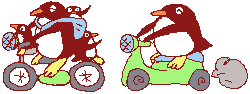夏休みの冒険[5]
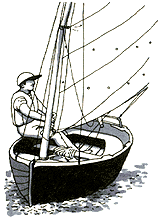
血沸き肉踊る冒険物語
長いようで短い夏休み。もう終わりだ。「結局今年も冒険をしなかったな」なんて思いながら、子供たちは読書感想文やドリルや絵日記の追い込みに入っているのではなかろうか。
そこで、今回は読書の冒険の話をしたい。課題図書のような有益な本もいいが、やはり夏休みには血沸き肉躍る冒険物語に熱中してほしいと思ってしまう。
冒険物というと、最近はファンタジーの方がおしているが、私にとってはマーク・トゥエインか海洋物である。
『ハックルベリー=フィンの冒険』の自由な空気、『宝島』や『十五少年漂流記』などの迫力満点の物語に、それこそ時間を忘れた体験が、その後の自分を形作っている。
イギリスを中心とするヨーロッパの海洋少年冒険小説のいいところは、子供を全く子供扱いしないところだ。子供が主人公であっても、子供言葉で書いたりしない。『宝島』でも船乗りの専門用語や船員の俗語、スペイン語らしい単語までがどんどん出てくる。
いったい向こうの子供たちはこれを読んで理解できるのだろうか。だが、その専門用語などは子供にとって読書の障害などではなく、本物の世界をのぞき込むような、ワクワク感に満ちたものなのである。
今年は「海の日」という祝日ができたが、今の日本は島国なのに海に親しんでいない。子供たちがボート遊びするうちに大海原に出てしまって、なんて設定は共感を得られまい。
それでも最近、シーカヤックも流行のきざしがあるし、イラストにあげたようなヨット「A級ディンギー」なども復活してきたらしく、海好き、船好きの私としてはうれしいかぎりだ。
このディンギーを駆って子供たちが夏休みの大冒険をするのがイギリスの少年冒険小説の決定版『ツバメ号とアマゾン号』だ。
この本をこれまで何度読み返したことか。イギリスのジャーナリスト、アーサー・ランサムの書いたこの作品も、冒頭から「間切る」とか「八点鐘」とか、専門用語のオンパレード。ぜひこの本に熱中して、少し大人びた顔で2学期を迎えてほしいものだ。
1996,8,29
文:石井研二 絵:石井光